「442」上映会終了
今年度最初のやんかれセミナーは、アメリカから映画監督のすずきじゅんいち(以降じゅんちゃん)、榊原るみ夫妻を招いて、去年公開されたドキュメンタリー映画「442日系部隊・アメリカ史上最強の陸軍」の上映会からスタートする。
上映会は22日だが、前日に監督を囲んでの交流会を行う為、21日に清水に入ってもらった。二人は去年ラスベガス近郊で交通事故を起こし重症を負った。一年ぶりに会ったじゅんちゃんは思ったより元気そうだったが、それでも体に残る傷跡は痛々しい。るみちゃんも手の指が曲がったままでまっすぐにならないという。
我が家で昼食をとり、3時から交流会の会場である清水産業・情報プラザに向かう。「監督を囲んで」と題して、ヤングカレッジ役員や、市内の映画愛好者に集まって貰い、約二時間ほど映画についてデスカッションを行った。最初はやや硬い感じでスタートしたが、暫くするといい雰囲気になってきて、冗談をいいながら監督やるみちゃんに映画についての質問が相次いだ。


そして5時に無事終了。実は5月21日は特別な日だった。じゅんちゃんの59歳の誕生日である。そして何を隠そう5月25日はオレの誕生日。そこで合同で誕生会をやろうと、前々から末廣鮨に予約を入れておいた。腹減らしに情報プラザから末廣まで歩こうということになり、ゆっくり歩き出した。
じゅんちゃん夫婦、オレ達夫婦、それにきくちゃん夫婦の計6人。15分ほど歩いて末廣鮨に到着。門のところに親方がいた。その日は個室を予約していたが、親方がカウンターに座ったらと言うので、カウンターに陣取った。まずは「末廣鮨」の美味しい冷酒で乾杯!よかったな~、じゅんちゃん、こうして又酒を一緒に飲めて嬉しいよ。美味しい魚と楽しい話で一年振りの再会を喜ぼう。
最後に、メロンにブランディをたっぷりかけて贅沢なデザートを楽しんでから、末廣鮨からタクシーで我家に帰った。冷蔵庫で冷やしておいた秘蔵のアイスワインで改めて乾杯。明日もあるので、早めに休むことにする。
22日はY君の車で上映会会場のサールナートホールに向かう。12時からマスコミ試写会だが、3時からの一般上映会が満席なのでこちらにも一般の人に入ってもらった。オレとじゅんちゃんも試写会が始まってからそっと潜り込んで映画を見た。


DVDでは観ているが、大画面で観ると迫力が違う。この映画に出てくる「442部隊」の兵士は、日系人と云われる米国人である。日本人ではないのだ。でもこころの中に間違いなく日本人の魂を持ち続けている。米国人である日系人の大和魂が、ヨーロッパ戦線で大きな犠牲を払いながら数々の戦果を挙げ、米国史上最強の陸軍と称されたのだ。その勇猛さが、その潔さが、観ているオレ達の日本人としての魂を揺すぶるのだろうか?
映画が終わったらパラパラと拍手が起きた。いつの間にか館内拍手になった。じゅんちゃんが思わず立ち上がって「ありがとうございます」と言った。余程嬉しかったんだろうね。
試写会が終わってからマスコミの囲み取材が始まった。静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ、SBSテレビ3局がカメラを回す。他に新聞社、ラジオと取材が続く。



3時からはいよいよ一般の上映会が始まる。雨模様で客の入りが心配だったが、瞬く間に席も埋まった。ヤングカレッジの抹茶教室の講師でもある南條さんが司会をし、理事長の桑添が開会の挨拶をしてから上映が始まった。じゅんちゃんはその間も控え室でマスコミの取材を受け続けている。



そして映画が終わり、舞台にじゅんちゃんとるみちゃんが登場。南條さんが仕切ってトークショーが始まった。二人の自己紹介から始まり、この映画を作った動機、そして制作エピソードなどが語られる。観客からの質問にも丁寧に答え、トークショーも無事終了した。そして江戸芸かっぽれ家元の櫻川ぴん助師匠から花束が贈られた。


出口ではテレビカメラが観客に感想を聞いていた。ありゃ~、うちのカミさんもカメラに捕まってる。何を話しているやら、、、ちと心配、、、NHK静岡の平山さんも映画を観に来てくれた。彼女にじゅんちゃんとるみちゃんを紹介した。平山さんもこの映画に大変興味を持ってくれたようだ。

そして客が帰ってから、ヤングカレッジの役員と今回のボランティアスタッフに残って貰い、じゅんちゃんとるみちゃんから御礼の挨拶をして貰った。ゆっくり歓談したかったが、二人は翌日佐渡島に行く予定という。30分程で解散して二人を駅まで送った。

昨日から慌しく時間が過ぎ去ってしまったが、今度はゆっくり会いたいものだ。数日後に二人はアメリカに帰る。帰れば日系ドキュメンタリー三部作の最後の作品「MIS」の編集が待っている。じゅんちゃんにはくれぐれも無理をしないで欲しい。まあ、るみちゃんというしっかり者の奥さんがいるから心配ないか、、、
嬉しいことに、次回作も今回と同じようにヤングカレッジが上映会をやりたいと役員が言ってくれている。何とか実現したいな~。オレもまだまだ頑張らなきゃ!!
上映会は22日だが、前日に監督を囲んでの交流会を行う為、21日に清水に入ってもらった。二人は去年ラスベガス近郊で交通事故を起こし重症を負った。一年ぶりに会ったじゅんちゃんは思ったより元気そうだったが、それでも体に残る傷跡は痛々しい。るみちゃんも手の指が曲がったままでまっすぐにならないという。
我が家で昼食をとり、3時から交流会の会場である清水産業・情報プラザに向かう。「監督を囲んで」と題して、ヤングカレッジ役員や、市内の映画愛好者に集まって貰い、約二時間ほど映画についてデスカッションを行った。最初はやや硬い感じでスタートしたが、暫くするといい雰囲気になってきて、冗談をいいながら監督やるみちゃんに映画についての質問が相次いだ。
そして5時に無事終了。実は5月21日は特別な日だった。じゅんちゃんの59歳の誕生日である。そして何を隠そう5月25日はオレの誕生日。そこで合同で誕生会をやろうと、前々から末廣鮨に予約を入れておいた。腹減らしに情報プラザから末廣まで歩こうということになり、ゆっくり歩き出した。
じゅんちゃん夫婦、オレ達夫婦、それにきくちゃん夫婦の計6人。15分ほど歩いて末廣鮨に到着。門のところに親方がいた。その日は個室を予約していたが、親方がカウンターに座ったらと言うので、カウンターに陣取った。まずは「末廣鮨」の美味しい冷酒で乾杯!よかったな~、じゅんちゃん、こうして又酒を一緒に飲めて嬉しいよ。美味しい魚と楽しい話で一年振りの再会を喜ぼう。
最後に、メロンにブランディをたっぷりかけて贅沢なデザートを楽しんでから、末廣鮨からタクシーで我家に帰った。冷蔵庫で冷やしておいた秘蔵のアイスワインで改めて乾杯。明日もあるので、早めに休むことにする。
22日はY君の車で上映会会場のサールナートホールに向かう。12時からマスコミ試写会だが、3時からの一般上映会が満席なのでこちらにも一般の人に入ってもらった。オレとじゅんちゃんも試写会が始まってからそっと潜り込んで映画を見た。
DVDでは観ているが、大画面で観ると迫力が違う。この映画に出てくる「442部隊」の兵士は、日系人と云われる米国人である。日本人ではないのだ。でもこころの中に間違いなく日本人の魂を持ち続けている。米国人である日系人の大和魂が、ヨーロッパ戦線で大きな犠牲を払いながら数々の戦果を挙げ、米国史上最強の陸軍と称されたのだ。その勇猛さが、その潔さが、観ているオレ達の日本人としての魂を揺すぶるのだろうか?
映画が終わったらパラパラと拍手が起きた。いつの間にか館内拍手になった。じゅんちゃんが思わず立ち上がって「ありがとうございます」と言った。余程嬉しかったんだろうね。
試写会が終わってからマスコミの囲み取材が始まった。静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ、SBSテレビ3局がカメラを回す。他に新聞社、ラジオと取材が続く。
3時からはいよいよ一般の上映会が始まる。雨模様で客の入りが心配だったが、瞬く間に席も埋まった。ヤングカレッジの抹茶教室の講師でもある南條さんが司会をし、理事長の桑添が開会の挨拶をしてから上映が始まった。じゅんちゃんはその間も控え室でマスコミの取材を受け続けている。
そして映画が終わり、舞台にじゅんちゃんとるみちゃんが登場。南條さんが仕切ってトークショーが始まった。二人の自己紹介から始まり、この映画を作った動機、そして制作エピソードなどが語られる。観客からの質問にも丁寧に答え、トークショーも無事終了した。そして江戸芸かっぽれ家元の櫻川ぴん助師匠から花束が贈られた。
出口ではテレビカメラが観客に感想を聞いていた。ありゃ~、うちのカミさんもカメラに捕まってる。何を話しているやら、、、ちと心配、、、NHK静岡の平山さんも映画を観に来てくれた。彼女にじゅんちゃんとるみちゃんを紹介した。平山さんもこの映画に大変興味を持ってくれたようだ。
そして客が帰ってから、ヤングカレッジの役員と今回のボランティアスタッフに残って貰い、じゅんちゃんとるみちゃんから御礼の挨拶をして貰った。ゆっくり歓談したかったが、二人は翌日佐渡島に行く予定という。30分程で解散して二人を駅まで送った。
昨日から慌しく時間が過ぎ去ってしまったが、今度はゆっくり会いたいものだ。数日後に二人はアメリカに帰る。帰れば日系ドキュメンタリー三部作の最後の作品「MIS」の編集が待っている。じゅんちゃんにはくれぐれも無理をしないで欲しい。まあ、るみちゃんというしっかり者の奥さんがいるから心配ないか、、、
嬉しいことに、次回作も今回と同じようにヤングカレッジが上映会をやりたいと役員が言ってくれている。何とか実現したいな~。オレもまだまだ頑張らなきゃ!!
2011年05月23日 Posted by 臥游山人 at 21:20 │Comments(0) │NPO法人ヤングカレッジ
田中智学と三保、そして宮沢賢治
羽衣伝説で有名な三保の内海貝島地区に、最勝閣という、まるで竜宮城のような建物があった。木造五階建てで外観は三階建て、何とも不思議な建物であった。明治43年に大阪の四ツ橋にあった立正閣を移築したもので、海を隔てた清水の市街からもその優雅な姿が望めたという。

最勝閣は国柱会の本部であった。国柱会の主宰者は田中智学という宗教家である。田中智学は宗教から国家観を構築して、法華経を国教とし、いずれ政治的にも思想的にも世界を統一し、世界に平和と繁栄をもたらすという、とてつもない野望を抱えていた。
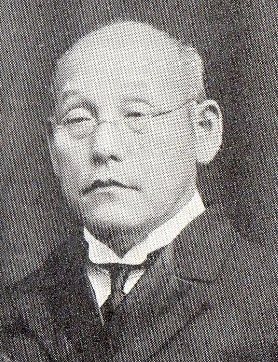
その為に、日蓮の教えにもとづき、日本最勝の地、霊峰富士山に国立戒壇を建立する。その富士山を遠望するに最適の地が三保である、ということで最勝閣を三保に築いたのだった。智学は、国教が成立して日本が統一された場合、清水を首都とし、三保に拝殿を建設し、清水港を母港とする義勇艦隊を置き、本山鉄道を敷くということを夢見ていたという。若しこれが実現していたら、、、と思うと、、、ぞくぞくするような話だね。

今思うとまさに夢物語に過ぎないが、当時は智学に心酔し、彼を信奉した人が沢山いた。高山樗牛、与謝野鉄幹・晶子夫妻、幸田露伴、高浜虚子、萩原井泉水、北原白秋、武見太郎、五代目尾上菊五郎、中村福助、近衛文麿、大川周明、井上日召、北一輝、牧口常三郎、など日本を代表するような文化人や思想家達、そして東条英機や石原莞爾などの軍人にも影響を与えた。田中智学によって造語された「八絋一宇」という思想が、東条英機により大東亜共栄圏の支配というイデオロギーにすり替えられ、石原莞爾が満州に国家を建国し、「王道楽土」、「五族協和」を唱え、やがて日華事変、大東亜戦争へと発展していくことになった。
なかでも特筆すべきは宮沢賢治の存在であろう。数々の作品から、宮沢賢治にはコスモポリタン的な、あるいはキリスト教的なイメージを抱く人もいるようだが、彼は生涯を通して日蓮主義に基く国柱会信者である。というより田中智学信者といってもいいかもしれない。賢治は、「日蓮上人に従い奉る様に、田中先生に絶対に服従いたします」と宣言している。又、賢治自身の戒名も「真金院三不日賢善男子」といい、国柱会より戴いている。

賢治の父親は、浄土真宗の熱心な門徒であったが、賢治は事あるごとに父親に改宗を迫り、二人は宗派を巡って争いが耐えなかったそうである。しかし何故か父親は、晩年になって日蓮宗に改宗しているという。あの有名な「雨ニモマケズ」は若しかしたら折伏の詩なのかもしれないナ~~。
賢治が26歳の時、最愛の妹トシが亡くなっている。しかし賢治は宗派が違うということでトシの葬儀に参列せず、後日、分骨したトシの遺骨を持って三保の最勝閣を訪れ納骨したのである。当時、巴川河口辺りから三保の塚間まで内海を横断する長い木橋があったという。果たして賢治はトシの遺骨を抱いてこの橋を渡ったのであろうか。ここで数日間過ごし賢治は東京に戻っていった。その時賢治は田中智学と何を語ったのであろうか?

その後、行政や企業による三保地区の開発が進み、それを嫌った智学は昭和4年に国柱会本部を東京に移転した。やがて最勝閣も取り壊された。その時智学はこんな言葉を残している。「天下の宝を破壊しないでも道はいくらもある。そこが人間の智慧の用かせ所だ。至誠もなく、経営もなく、智慧もない奴がやった政治経済は、天下の自然の大宝物を破壊する様になる。これを愚劣という」
時を同じくして、清水では異端の宗教家が蠢いていた。審神者(さにわ)の長澤雄楯(かつたつ)である。元「美穂神社」の宮司で、現在の清水区岡町にある「月見里(やまなし)笠森稲荷」の宮司であった長澤雄楯は、神社を尋ねてきた出口王仁三郎に鎮魂帰神法を施し、神懸り状態にさせたという。二人は手を洗い、口をすすいで社前で対座し、鎮魂石の前で長澤が岩笛を吹きだした。みるみる王仁三郎の体がぴ~んと反り返り神懸り状態になった。この時王仁三郎は日露戦争の開戦日や勝敗まで言い当てたという。
長澤雄楯の影響を受けた宗教家は数知れないが、中でも三五(あなない)教を興した中野與之助が有名である。三五教本部は笠森稲荷の直ぐ横にあったが、今は大東町に移設した。余り知られていないが、NGO団体の「オイスカ」はこの三五教が創設したものである。
その他にもPL教の本部も清水にあった。PL教はその頃まだ「ひとのみち」と呼ばれていたが、清水駅の近くに本部があり、多い時で10万人を越える信者がいたという。やがて清水の馬走という所に本部を移設しようとして地元住民の反対で頓挫したという。それを聞きつけた大阪富田林の塩川正三という人が誘致に動き、現在に至った。塩川正三は、あの塩爺こと塩川正十郎の父親である。
調べれば調べるほど、清水は奥が深い。しかし富士山は微動だにせず、そんな塵芥の移り変わりを悠然と見届け続けている、、、


最勝閣は国柱会の本部であった。国柱会の主宰者は田中智学という宗教家である。田中智学は宗教から国家観を構築して、法華経を国教とし、いずれ政治的にも思想的にも世界を統一し、世界に平和と繁栄をもたらすという、とてつもない野望を抱えていた。
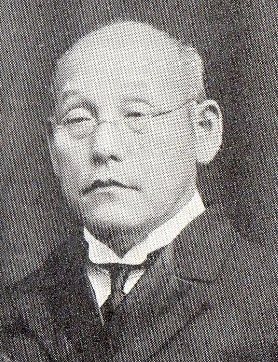
その為に、日蓮の教えにもとづき、日本最勝の地、霊峰富士山に国立戒壇を建立する。その富士山を遠望するに最適の地が三保である、ということで最勝閣を三保に築いたのだった。智学は、国教が成立して日本が統一された場合、清水を首都とし、三保に拝殿を建設し、清水港を母港とする義勇艦隊を置き、本山鉄道を敷くということを夢見ていたという。若しこれが実現していたら、、、と思うと、、、ぞくぞくするような話だね。

今思うとまさに夢物語に過ぎないが、当時は智学に心酔し、彼を信奉した人が沢山いた。高山樗牛、与謝野鉄幹・晶子夫妻、幸田露伴、高浜虚子、萩原井泉水、北原白秋、武見太郎、五代目尾上菊五郎、中村福助、近衛文麿、大川周明、井上日召、北一輝、牧口常三郎、など日本を代表するような文化人や思想家達、そして東条英機や石原莞爾などの軍人にも影響を与えた。田中智学によって造語された「八絋一宇」という思想が、東条英機により大東亜共栄圏の支配というイデオロギーにすり替えられ、石原莞爾が満州に国家を建国し、「王道楽土」、「五族協和」を唱え、やがて日華事変、大東亜戦争へと発展していくことになった。
なかでも特筆すべきは宮沢賢治の存在であろう。数々の作品から、宮沢賢治にはコスモポリタン的な、あるいはキリスト教的なイメージを抱く人もいるようだが、彼は生涯を通して日蓮主義に基く国柱会信者である。というより田中智学信者といってもいいかもしれない。賢治は、「日蓮上人に従い奉る様に、田中先生に絶対に服従いたします」と宣言している。又、賢治自身の戒名も「真金院三不日賢善男子」といい、国柱会より戴いている。

賢治の父親は、浄土真宗の熱心な門徒であったが、賢治は事あるごとに父親に改宗を迫り、二人は宗派を巡って争いが耐えなかったそうである。しかし何故か父親は、晩年になって日蓮宗に改宗しているという。あの有名な「雨ニモマケズ」は若しかしたら折伏の詩なのかもしれないナ~~。
賢治が26歳の時、最愛の妹トシが亡くなっている。しかし賢治は宗派が違うということでトシの葬儀に参列せず、後日、分骨したトシの遺骨を持って三保の最勝閣を訪れ納骨したのである。当時、巴川河口辺りから三保の塚間まで内海を横断する長い木橋があったという。果たして賢治はトシの遺骨を抱いてこの橋を渡ったのであろうか。ここで数日間過ごし賢治は東京に戻っていった。その時賢治は田中智学と何を語ったのであろうか?

その後、行政や企業による三保地区の開発が進み、それを嫌った智学は昭和4年に国柱会本部を東京に移転した。やがて最勝閣も取り壊された。その時智学はこんな言葉を残している。「天下の宝を破壊しないでも道はいくらもある。そこが人間の智慧の用かせ所だ。至誠もなく、経営もなく、智慧もない奴がやった政治経済は、天下の自然の大宝物を破壊する様になる。これを愚劣という」
時を同じくして、清水では異端の宗教家が蠢いていた。審神者(さにわ)の長澤雄楯(かつたつ)である。元「美穂神社」の宮司で、現在の清水区岡町にある「月見里(やまなし)笠森稲荷」の宮司であった長澤雄楯は、神社を尋ねてきた出口王仁三郎に鎮魂帰神法を施し、神懸り状態にさせたという。二人は手を洗い、口をすすいで社前で対座し、鎮魂石の前で長澤が岩笛を吹きだした。みるみる王仁三郎の体がぴ~んと反り返り神懸り状態になった。この時王仁三郎は日露戦争の開戦日や勝敗まで言い当てたという。
長澤雄楯の影響を受けた宗教家は数知れないが、中でも三五(あなない)教を興した中野與之助が有名である。三五教本部は笠森稲荷の直ぐ横にあったが、今は大東町に移設した。余り知られていないが、NGO団体の「オイスカ」はこの三五教が創設したものである。
その他にもPL教の本部も清水にあった。PL教はその頃まだ「ひとのみち」と呼ばれていたが、清水駅の近くに本部があり、多い時で10万人を越える信者がいたという。やがて清水の馬走という所に本部を移設しようとして地元住民の反対で頓挫したという。それを聞きつけた大阪富田林の塩川正三という人が誘致に動き、現在に至った。塩川正三は、あの塩爺こと塩川正十郎の父親である。
調べれば調べるほど、清水は奥が深い。しかし富士山は微動だにせず、そんな塵芥の移り変わりを悠然と見届け続けている、、、


